こんにちは。
琴×リコーダー『ののアンサンブル』お琴担当たぬきです。
今日は楽譜についての話です。
ののアンサンブルの楽譜は、今のところほぼ全てかえる氏が編曲し、五線譜を書いてくれています。
しかし、お琴の楽譜は五線譜ではありません。
がんばれば五線譜でも弾けますが、通常は漢数字と漢字、数字を縦に書いてる楽譜を使用します。
お琴は絃に数字や漢字が割り当てられており、お琴(13絃)は「一~十と斗、為、巾」を、17絃は「一~十と1~7」を使用します。
つまり、上記の漢数字と漢字と数字が読める人なら、理屈上は誰でも楽譜を理解できるのです。
たぬきの学生の頃には、お琴やってみたいALTの先生(楽器経験者)が、がんばって漢数字と漢字を覚えてものすごく上手に弾いていたこともありました。
そしてこれは、かえる氏からの楽譜をたぬきが弾くまでの長い道のりの物語です。

ここに五線譜ありけり。
かえる氏が編曲して五線譜をつくり、たぬきに渡されました。

まずは調絃を考えます。
一番上ある「一~十、1~7」とアルファベット(ドイツ音名)が調絃です。チューナーを使って、この音に合わせていこうとしています。
今回は#も♭もなさそうなので、とりあえず標準の調絃でチャレンジします。
調絃を決めたら、その通りに音符の下に漢数字たちを書き込んでいきます。
ドなら~Cだから~一か八か5でぇ~
みたいなことを永遠に繰り返します。
身体から遠い漢数字の一~四あたりは腰が痛くなるので、五~十と1~7をなるべく使うよう考えながら書いていきます。
前はこれがめちゃくちゃ時間かかったんですが、今では呼吸するように書けるようになりました。しかし読みながら変換して演奏するレベルには至らず。
もうめんどくさいから五線譜のままでいいよ!とか、リズムが面倒だから五線譜のほうがいいよ!っていうときは、この状態のまま演奏します。

はい。お琴用の楽譜です。
縦書きの縦譜さんです。
細長い四角が1小節
それが4つの部屋にわかれた1部屋が4分音符
1部屋を半分に区切って8分音符
区切られた空間に2つ書けば16分音符
音を鳴らすときは漢数字などを記入
休符は◯(4分休符)、△(8分休符)、伸ばしたい音は真ん中に黒い●が入るよ
みたいなルールなので、五線譜読めないけど縦譜は読めた!という人がわりといます。
最近、縦譜はマジックで書いたほうが見やすいという気付きを得ました。
とりあえず、縦譜ができたのでお琴を弾くことができるようになりました。
しかしまだ旅は終わりません。

弾くときに弾きやすいように、または音色を変えるため、もしくは手が届かないなど様々な理由により、追加の記号を書いていきます。
写真の譜面で言うと、左手でピチカートする音は、漢数字を丸で囲んでいます。
ちなみに右手でピチカートするときは、右上に小さく4って書きます。
これは親指(1)、人差し指(2)、中指(3)、薬指(4)という運指のための番号です。
正直てきとうに手書きすると4の音なのか運指の4なのか自分でもわからなくなるときがあります。
他にも必要な記号を弾きながら考え、書き込んでいきます。
ののアンサンブルで弾くときは、合奏してみて変えることも多いです。

めんどくさいリズムだあ、という顔をして縦譜に直します。

たぶんこんなかんじ、と思いながら縦譜に直しました。
ちなみに前の楽譜でも1回縦譜に直すところまでやったんですが、弾いてみたら音が多すぎてかえる氏の思ってたんと違ったらしく、後日「ちょっと直すわ~」と言われだいぶ丸ごと変わってしまったのでしょんぼりしながら直した部分です。
こんなかんじでがんばって縦譜に直し、弾いてみて物理的に無理なところはかえる氏に相談し、修正してもらい、合奏してみてかえる氏の脳内ミュージックと合っているか確認し、また修正して、という工程を経てようやく「本番のために練習しよう」というところへたどり着きます。長いよ。
かえる氏は「お琴のポテンシャルがよくわかってない」と言うし、たぬきも「お琴のポテンシャルとは?」というような状態からはじまったののアンサンブルなので、最初の頃は「こりゃ~~~無理よ」みたいな楽譜が来ていたものです。
それを思えばかなり弾きやすくはなった。
そのへんの話もまた記事にしたいと思います。
かえる氏が楽譜作るときに参考にしてくれそうな内容を……
以上、お琴担当たぬきでした。
ブログ村ランキングに参加しています。
お暇な方は下のボタン押していただくとたぬきのやる気が上がります。
『ののぶろぐ』押してもらえばまたこちらのブログに戻ってこられます。

にほんブログ村
琴×リコーダー『ののアンサンブル』お琴担当たぬきです。
今日は楽譜についての話です。
ののアンサンブルの楽譜は、今のところほぼ全てかえる氏が編曲し、五線譜を書いてくれています。
しかし、お琴の楽譜は五線譜ではありません。
がんばれば五線譜でも弾けますが、通常は漢数字と漢字、数字を縦に書いてる楽譜を使用します。
お琴は絃に数字や漢字が割り当てられており、お琴(13絃)は「一~十と斗、為、巾」を、17絃は「一~十と1~7」を使用します。
つまり、上記の漢数字と漢字と数字が読める人なら、理屈上は誰でも楽譜を理解できるのです。
たぬきの学生の頃には、お琴やってみたいALTの先生(楽器経験者)が、がんばって漢数字と漢字を覚えてものすごく上手に弾いていたこともありました。
そしてこれは、かえる氏からの楽譜をたぬきが弾くまでの長い道のりの物語です。

ここに五線譜ありけり。
かえる氏が編曲して五線譜をつくり、たぬきに渡されました。

まずは調絃を考えます。
一番上ある「一~十、1~7」とアルファベット(ドイツ音名)が調絃です。チューナーを使って、この音に合わせていこうとしています。
今回は#も♭もなさそうなので、とりあえず標準の調絃でチャレンジします。
調絃を決めたら、その通りに音符の下に漢数字たちを書き込んでいきます。
ドなら~Cだから~一か八か5でぇ~
みたいなことを永遠に繰り返します。
身体から遠い漢数字の一~四あたりは腰が痛くなるので、五~十と1~7をなるべく使うよう考えながら書いていきます。
前はこれがめちゃくちゃ時間かかったんですが、今では呼吸するように書けるようになりました。しかし読みながら変換して演奏するレベルには至らず。
もうめんどくさいから五線譜のままでいいよ!とか、リズムが面倒だから五線譜のほうがいいよ!っていうときは、この状態のまま演奏します。

はい。お琴用の楽譜です。
縦書きの縦譜さんです。
細長い四角が1小節
それが4つの部屋にわかれた1部屋が4分音符
1部屋を半分に区切って8分音符
区切られた空間に2つ書けば16分音符
音を鳴らすときは漢数字などを記入
休符は◯(4分休符)、△(8分休符)、伸ばしたい音は真ん中に黒い●が入るよ
みたいなルールなので、五線譜読めないけど縦譜は読めた!という人がわりといます。
最近、縦譜はマジックで書いたほうが見やすいという気付きを得ました。
とりあえず、縦譜ができたのでお琴を弾くことができるようになりました。
しかしまだ旅は終わりません。

弾くときに弾きやすいように、または音色を変えるため、もしくは手が届かないなど様々な理由により、追加の記号を書いていきます。
写真の譜面で言うと、左手でピチカートする音は、漢数字を丸で囲んでいます。
ちなみに右手でピチカートするときは、右上に小さく4って書きます。
これは親指(1)、人差し指(2)、中指(3)、薬指(4)という運指のための番号です。
正直てきとうに手書きすると4の音なのか運指の4なのか自分でもわからなくなるときがあります。
他にも必要な記号を弾きながら考え、書き込んでいきます。
ののアンサンブルで弾くときは、合奏してみて変えることも多いです。

めんどくさいリズムだあ、という顔をして縦譜に直します。

たぶんこんなかんじ、と思いながら縦譜に直しました。
ちなみに前の楽譜でも1回縦譜に直すところまでやったんですが、弾いてみたら音が多すぎてかえる氏の思ってたんと違ったらしく、後日「ちょっと直すわ~」と言われだいぶ丸ごと変わってしまったのでしょんぼりしながら直した部分です。
こんなかんじでがんばって縦譜に直し、弾いてみて物理的に無理なところはかえる氏に相談し、修正してもらい、合奏してみてかえる氏の脳内ミュージックと合っているか確認し、また修正して、という工程を経てようやく「本番のために練習しよう」というところへたどり着きます。長いよ。
かえる氏は「お琴のポテンシャルがよくわかってない」と言うし、たぬきも「お琴のポテンシャルとは?」というような状態からはじまったののアンサンブルなので、最初の頃は「こりゃ~~~無理よ」みたいな楽譜が来ていたものです。
それを思えばかなり弾きやすくはなった。
そのへんの話もまた記事にしたいと思います。
かえる氏が楽譜作るときに参考にしてくれそうな内容を……
以上、お琴担当たぬきでした。
ブログ村ランキングに参加しています。
お暇な方は下のボタン押していただくとたぬきのやる気が上がります。
『ののぶろぐ』押してもらえばまたこちらのブログに戻ってこられます。
にほんブログ村









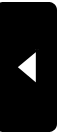

コメント